業務引き継ぎマニュアル|スムーズな退職と円満な人間関係のために

退職の際に、避けて通れないのが「業務の引き継ぎ」です。
いくら優秀な人でも、引き継ぎがうまくいかなければ、会社に迷惑をかけるだけでなく、自分の評価を下げることにもなりかねません。
また、良い引き継ぎをすることでその後の良好な人間関係にも繋がり、その人間関係が退職後の『貴重な自分の資産』になることも少なくありません。
この記事では、退職時における業務引き継ぎの重要性から、引き継ぎ内容の整理方法、マニュアルの作成手順、後任者とのやり取り、そして引き継ぎ完了後に送るメールの例文まで、退職するすべての人が知っておくべき情報を網羅的に解説します。
引き継ぎも含めた退職全体の流れはこちらの記事をぜひ参照してください。
≫【保存版】正社員の退職の仕方|円満に辞めるための手順と注意点
退職時の引き継ぎが重要な理由
退職後、自分の業務を誰かが代わりに担うことになります。
万が一、適切な引き継ぎがされていない場合は、以下のような問題が発生します。
- 取引先とのトラブル(連絡漏れ、納期遅れなど)
- 社内の混乱(業務の停滞、対応ミス)
- 自分の評価低下(無責任な退職と見なされる)
- 後任者や残った社員への迷惑
引き継ぎは単なる作業ではなく、「自分の担当業務を後任者がスムーズに遂行できるようにする」ための退職前の最後の仕事です。
引き継ぎが必要な業務の洗い出し
まずは自分が日常的に行っている業務をすべて書き出してみましょう。
最初から1つ1つの業務の内容を細かく掘り下げていくと洗い出すべき業務を見落としてしまう可能性があるため、まずは粗くても良いので、リスト形式で書き出してみると良いでしょう。
例:
- SNS運用(X、Instagramの更新)
- SNS運用レポートのまとめ
- 顧客との打ち合わせ
- 上司への週次の報告
- 新規顧客との営業の打ち合わせへの参加
- 顧客への成果レポートの送信
- 全社表彰式のヘルプ
- 経費処理清算
- 営業会議への参加
- 顧客への請求書の発行
- セミナー参加
業務を行うタイミングの整理
次に、リスト形式でまとめたものを、日次、週次、月次、年次とその業務を行っているタイミングごとに整理し、おおまかでも良いので、所要時間も書いてみましょう。そうすることで、後任者にとってわかりやすいまとめかたになります。
【例】
- 日次
・SNS運用(X、Instagramの更新)
・SNS運用レポートのまとめ - 週次
・上司への週次の報告
・顧客への成果レポートの送信
・毎週火曜日10時からの営業会議 - 月次
・経費処理清算
・顧客への請求書の発行 - 年次
・全社表彰式のヘルプ - 随時
・顧客との打ち合わせ
・セミナー参加
・新規顧客との営業の打ち合わせへの参加
業務マニュアルの作成手順とコツ
次にリスト形式で洗い出した業務をもとに後任者に引き継ぐための業務マニュアルを作成してみましょう。
業務マニュアルをまとめる際、各業務のまとめ方で必要な構成は次のとおりです。
業務引き継ぎマニュアルの構成
1.業務名
例えば「月次請求書の発行業務」といったようにどの業務についてのマニュアル化を具体的に書きましょう。
2.業務の目的(なぜ必要なのか)
作業手順の理解ができていても「なぜその業務を行うのか」という目的がきちんと伝わっていないと、今後業務が変わったりした場合に本来の目的が達成されない場合があります。必ず「なぜその業務が必要なのか」という目的を伝えるようにしましょう。
3.業務実施のタイミング(いつその業務を行うのか)
いつその業務を行うのか、その業務開始のトリガーは何かなどを伝えておくと、後任者が安心できるとともに業務を忘れて実行しないということが少なくなります。
4.所要時間(その業務を行うためにどのくらいの時間がかかるのか)
引き継ぐ業務は1つではないことがほとんどです。またその業務を未経験の場合には「完了するのにどのくらいの時間がかかるのか」という目安をつかみづらいことが多いです。そのため、その業務を行うために必要な時間の目安を伝えてあげると、後任者が安心できます。
5.手順(フローや画像付きだと尚良し)
文章のみだと後任者がその業務を具体的にイメージしづらい場合もあります。そのため、業務のフローがあると良いでしょう。また、パソコンを使った仕事の場合は、実際に操作する画面のキャプチャもあるとわかりやすさが増します。
6.注意点(失敗例・よくあるミス)
自分が失敗した点、失敗しないために注意していた点も漏れずに伝えておきましょう。こういった点は経験者だからこそわかる部分も多く、後任者が未経験者の場合は大変貴重な情報になります。自分がしたミスを伝えるのは恥ずかしさもあるかもしれませんが、隠さず引き継ぎをすることで、後任者にとって安心感につながり、あなたへの信用も増すでしょう。
7.連絡先や依頼先一覧
1人で完結する業務ばかりではありません。その業務を開始したり、終了したりするためには他の多くの関係者が必要な場合もあります。そのため、その業務に関係する人が誰か、どのように連絡するかもまとめておきましょう。
8.その他の資料
業務を実行する際に参考にすべき資料があれば、その資料の名前や保存先(フォルダなど)も忘れずに伝えるようにしましょう。
後任者への引き継ぎ時に気をつけるべきポイント
退職時に業務マニュアルを作成する大切な目的の1つは「後任者がスムーズに業務を引き継げるようにすること」です。
そのため、以下のポイントに気をつけましょう。
1.できるだけ専門用語の使用は避ける
業務経験が長いと当たり前のように専門用語や業界用語を使ってしまう場合もありますが、後任者はそれらを知らない場合もあります。マニュアルを作成する際は、可能な限り一般人でもわかるような平易な表現を使いましょう。
また、専門用語を使う場合は後任者が理解できるように注釈も加えると良いでしょう。
2.マニュアルを渡して終わりにしない
必ず口頭でも説明の機会をつくり、後任者からの質問も聞きましょう。可能であれば作成したマニュアルをもとに一緒に業務を行いながら引き継ぎするのがベストです。
3.マニュアルの完成は後任者に任せる
いくら自分が一生懸命作ったマニュアルでも、後任者が理解できなければ意味はありません。マニュアルは最終的には後任者が自分で見てわかりやすいものになるようにしてもらうと良いでしょう。そのためには、Google DriveやMicrosoft365、Notionなど複数人が共同で編集できるツールを使うことも検討しましょう。
4.関係者への情報共有も忘れずに
後任者と引き継ぎをしている(した)ことが業務の関係者(同じ組織のメンバーや社外の関係者)にも忘れずに伝えておきましょう。「何をどこまで引き継ぎしたのか」という情報共有をしっかり行うことで、後任者の仕事もやりやすくなります。
関係者への情報共有の仕方については次の章でも説明をしていきます。
関係者への連絡の例文
前の章でも書いたように、業務の引き継ぎは後任者だけに行うのではなく、業務の関係者にも引き継ぎについて情報共有しておくことが大切です。
以下の例文を参考に、退職の挨拶もかねて社内外への関係者への連絡をしておきましょう。
社内への連絡例
業務に関係する社内の後任者以外への連絡例です。
件名:業務引き継ぎ完了のご報告
お疲れ様です。
○○部の○○です。
このたび私の退職にともない、担当していた以下の業務について、後任の●●さんへの引き継ぎをいたしましたので、ご報告いたします。【引き継ぎ業務】
・クライアント対応
・請求関連業務
・○○ツールの管理私の最終出社日は○月○日となっております。
○月○日までは●●さんに引き継ぎつつ、業務を担当しております。
万が一不備などございましたら、お手数ですがご連絡いただけますと幸いです。短い間でしたが、皆さまには大変お世話になりました。心より感謝申し上げます。
○○部 ○○
社外への連絡例
社外の取引先への連絡例です。
ただし、社外の取引先には退職については触れずに、担当者の変更として連絡した方が良い場合もあります。
社外の関係者には、どのような連絡をしておけば良いかは会社の方針や上司の判断にしたがってください。
また、メールで挨拶をする場合には、送信時にCCに上司、後任者を入れた方が良いこともありますので、上司に相談をしてください。
件名:担当者変更のご挨拶
株式会社○○
○○様いつも大変お世話になっております。
株式会社△△の○○です。私事で恐縮ですが、○月○日をもって退職することとなりました。
いたらぬ対応も多かったかと存じますが、○○様には大変お世話になり、感謝しております。
今後のご対応につきましては、後任の●●(○○@△△.co.jp)が引き継がせていただきます。また、●●からもご挨拶もかねてご連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。短い間ではありましたが、大変お世話になり、誠にありがとうございました。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
株式会社△△
○○
まとめ
退職時の業務引き継ぎは、会社や後任者のためだけでなく、自分自身のためでもあります。
準備をしっかりしつつ、最終出社日まで誠意を持った対応をしましょう。
【今日からできる引き継ぎ準備チェックリスト】
- 担当業務の洗い出し
- 業務マニュアルの作成
- 後任者との面談・説明日程の調整
- 引き継ぎ完了メールの作成
- 感謝の言葉で締めくくる退職
しっかりとした引き継ぎをすることで、「あの人がいたから助かった」と思われる最後のチャンスにもなります。
スムーズで丁寧な引き継ぎを行い、気持ちよく次のステップに進みましょう。
業務引き継ぎを終えて、次のステップをお探しの方は↓
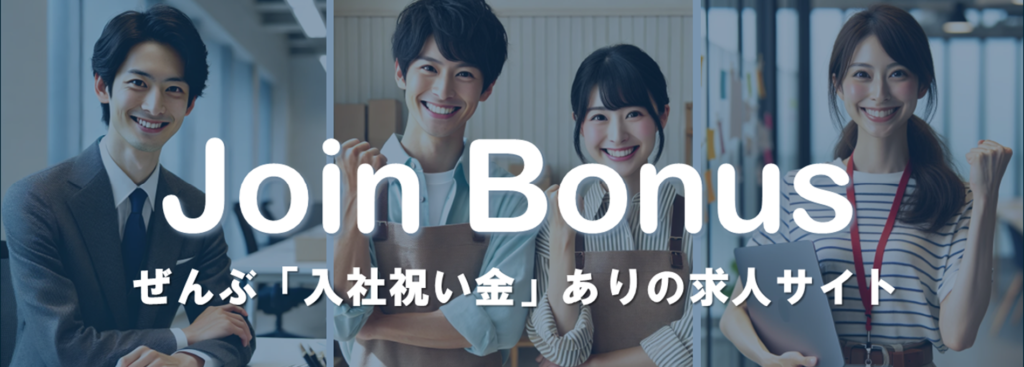
社員の離職に備えて人材の採用をお考えの企業様は↓



